学問の神様として親しまれている菅原道真。
道真を祀っている天満宮や天神社は全国で12000カ所あるとされていて、特に受験シーズンには多くの参拝客が訪れます。
《太宰府天満宮》福岡県太宰府市宰府4丁目7-1
朝8時に到着。まだ参拝客も少なく、神職さん達の掃除をする、ほうきの音が聞こえてくる🧹
太宰府天満宮は菅原道真公をお祀りする神社。学問の神、誠心の神として崇敬を集め、年間650万人の参拝がある
写真
①太鼓橋
②手水舎(一枚岩)
③楼門
④本殿
👇へ pic.twitter.com/51fDzEGGOu— 桃代 (@momookimomo) June 14, 2022
そんな菅原道真ですが、一時期は怨霊として京の都を大混乱にしたと人々から恐れられていたのですよ。
そんな怨霊がなぜ神様になったのか?ズバリ3分で紹介するコーナーです。
ポイントは3つです。
①京から九州へ左遷→失意の中亡くなる→怨霊となって京が大混乱!?→太政大臣になる→天神様となる
②ひたすら勉強の日々をおくっていた道真だが、苦手なものもあった!
③道真といえば梅!天満宮に彩る梅の名所は全国各地にある
左遷されて怨霊になり、さいごに神様になったスゴイ人!それが菅原道真
なぜ怨霊になった道真が神様になったの?

菅原道真が生まれた菅原家は学者の家系で、祖父の清公は遣唐使に随行して中国に留学経験があり、父の是善は史書「日本文徳天皇実録」の編纂に参加するなどしています。
そんな恵まれた環境の中で道真は学者としての才能を開花させて、25歳の若さで国家試験の最高峰だった方略試に及第すると、官僚としてのエリートコースを歩むことになります。
京では宇多天皇から絶大なる信頼を受けて、出世に出世を重ねてついに右大臣に就任します。
当時道真と共に右大臣だった藤原良世や中納言藤原時平は、宇多天皇が道真ばかりを頼っている状況が面白くなかったのです。
そもそも右大臣という地位は、当時藤原氏や皇族以外ではめったに就けないとされており、道真に対して反感を抱く貴族は少なくなかったのです。
実際道真は右大臣就任依頼を受けても何回か断っているのですが、それが受け入れられる事はありませんでした。
道真は右大臣になるのを自ら望んでいる訳では決してなかったのです。
その後最大の味方だった宇多天皇が出家した直後から、道真に対する反感が一気に表面化してしまいます。
右大臣に任じられた翌年の西暦900年、道真に対し天皇を廃立しようとしている嫌疑を一方的に掛けられて、太宰権帥として九州下向を命じられます。
当時醍醐天皇が発した勅書には、「本来なら法律によって処罰されるべきだが、温情によって太宰権帥とする」とあります。
事件の首謀者は、反道真勢力の中心だった左大臣・藤原時平であり、菅原家一門を一掃しようとした陰謀だといわれています。
息子たちもそれぞれ地方へと追放され、一家離散に追い込まれた道真は、一切の弁解を許されないまま失意の内に太宰府へ赴くのです。
罪人同様の待遇で太宰府に着いた道真でしたが、もともと体は弱くしだいに寝込む事が多くなってしまいました。
903年に道真は「他国で死んだ者は、遺骸を故郷に返すのが普通だが、自分はそれを望まない」として、太宰府に葬るようにと遺言。
その歳の2月、寂しくその人生の幕を下ろします。享年58歳。
901年に道真が太宰府に左遷された後、京では政務の指揮を藤原時平が行い、醍醐天皇の親政という表向きの形を取りながら藤原氏の権力を背景にさまざまな改革を推進。
国家財政の改善・繁栄をもたらされたと評価される一方、京では天変地異が相次ぐようになり、道真の左遷にかかわった人々に次々と不幸が襲いかかります。
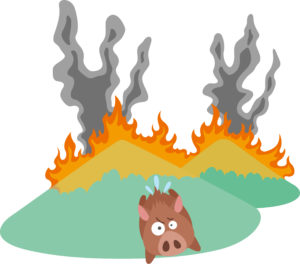
当時の人々はそう噂していましたが、ついに909年左遷をたくらんだ張本人とされる時平が病死します。
時平の両耳からヘビに姿を変えた道真の怨霊がはい出てきて、時平の病状が急変し息をひきとったという「北野天神縁起絵巻」にもその様子が描かれています。
真偽のほどはともかく、時平が亡くなってからも異変や怪事件が収まることはなく、慌てた朝廷は道真を生前の右大臣の職に戻し、正二位を追贈。
さらには太宰権帥に左遷した勅書を破棄しましたが、それでも効果なしとみると、993年道真は左大臣を贈られ、その後人臣としては最高の栄位である太政大臣を追加されました。
その後は道真の怨霊としての側面はしだいに過去のものとなり、天神様としての信仰が全国に広がる事になります。
左遷されて怨霊となり、神様になった菅原道真・・・改めてスゴイ人だと思いませんか?
学問も弓の名手でもあった道真だが、琴だけはムリだった!
 「松崎天神縁起絵巻」には、弓を射る道真が描かれており、学問だけでなく武芸の心得もあったようです。
「松崎天神縁起絵巻」には、弓を射る道真が描かれており、学問だけでなく武芸の心得もあったようです。
そんな何でもこなせるスーパースター道真ですが、一つだけ習っても習得できないモノがありました。
当時は琴が学者の支えになるものと考えられており、道真も習っていたのですが、こればかりはどんなに練習してもあまり上達しなかったようです。
結局琴をあきらめて、詩作の道に専念する事を道真は決意しています。
「弾琴を習うことを停む」という詩には、菅原家は文学の家だから、琴よりは詩に向いているんだという道真の開き直りが見て取れます。
学問の神様でも苦手なものがあったんだと知ると、なんだか親近感が沸いてきますね。
道真といえば梅!天神様ゆかりの地には梅がある
琴が弾けず、酒もあまり飲めなかった道真ですが、小さい頃から梅が大好きだったようです。
幼い頃に早くも梅を題材にした和歌を詠んだといわれ、はじめてつくった漢詩も梅についてでした。
道真の邸宅には梅の木が植えられて、「紅梅殿」と呼ばれていました。
道真が左遷させられて、京から太宰府へ向かう途中に立ち寄ったとされる場所の一つが、この愛媛県今治市の綱敷天満宮です☟

そして綱敷天満宮のすぐ近くには400本以上の梅の木があります。



春の訪れを感じる事が出来る梅ですが、学問の神様「菅原道真」のパワーを少し分けてもらいにみなさんも行ってみませんか?
【2020年版】愛媛県梅の名所の最新情報【西条市民の森・今治綱敷天満神社】
2020年は梅の見ごろが全国的に例年よりも早いようです。 このブログでは、愛媛県の梅の名所の最新情報を写真と共にお届けします。





